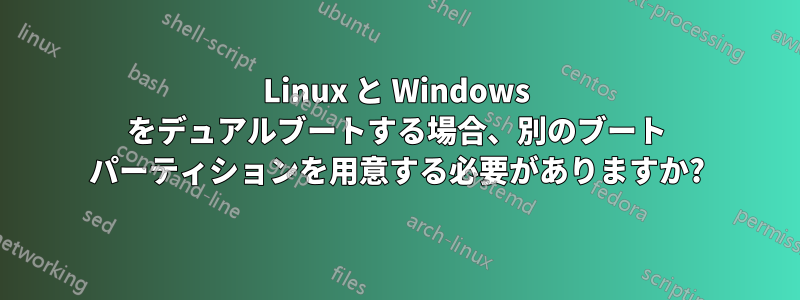
最近のLinuxディストリビューションをインストールする場合、通常は別の は必要ありませんが/boot、する別々のパーティションが必要になる特殊な状況/シナリオがあるようです/boot 。Linux と Windows のデュアル ブートもそのような状況の 1 つであるかどうか疑問に思っています。もしそうなら、その理由を説明していただければ幸いです。
答え1
最近のUEFIシステムでは、EFIシステムパーティション(略してESP、ファームウェアがブートローダーをロードするパーティション)は、ディストリビューションに応じて、/boot/efiまたはにマウントされます/boot。一部のディストリビューションでは、通常の使用ではESPが完全にアンマウントされています。しかし、それがどこにあるかを知る必要がある必要に応じてブートローダまたはその設定を更新するため。
ESP は、十分なスペースがあれば Windows ブートローダー (または UEFI 仕様に準拠した任意の OS のブートローダー) と共有できます。また、Linux と Windows を別のディスクにインストールしている場合は、各ディスク/OS に専用の ESP を用意できます。各ディスクに専用の ESP を用意しておくと、将来、OS を再インストールせずにディスクを別のコンピューターに移動したい場合、作業が簡単になります。各ディスクは、他のディスクの存在に依存せずに単独で起動できます。
ESP はファームウェアでサポートされているファイルシステム タイプを使用する必要があります。UEFI 仕様では FAT32 のサポートが保証されていますが、ハードウェア ベンダーは他のファイルシステムのサポートも選択する場合があります。ネイティブ Linux ファイルシステムがサポートされる可能性は低いため、ルート パーティションを ESP として指定することはできません。
/bootこれは、従来の BIOS システムでのパーティションの使用とは異なります。
1990 年代後半から 2004 年頃までの BIOS ベースのシステムでは、ディスクのサイズが BIOS 拡張の仕様が追いつけないほど急速に増大しました。2003 年には、現在標準となっている LBA48 アクセス メソッドが指定され、最大 128 ペタバイトの範囲のディスク サイズがサポートされるようになりました。
BIOS機能を使用してディスクのフルサイズにアクセスできない古いBIOSを搭載したシステムでは、ブートローダ、カーネル、およびinitramfsファイルが、BIOSが使用できるディスク領域の範囲内で、ディスクの先頭近くに配置されていることを確認することが重要です。できるアクセス。適切な場所とサイズの別のパーティションにすべてを配置することが、/bootこれを実現する確実な方法の 1 つです。このような制限がない場合は、/boot従来の意味でのパーティションは必要ありません。
GRUB の最新バージョンには、直接 ATA および AHCI サポートが含まれるようになりました。これを使用すると、GRUB が BIOS をバイパスしてディスク コントローラ ハードウェアを直接操作することで、これらの BIOS 制限を回避することもできます。ただし、使用するディストリビューションによっては、このようなサポートがデフォルトで有効になっていない場合があります。これは、対応する BIOS ベースのコードに比べてテストが不十分で、これらの機能に関するドキュメントが非常に少ないためです。


