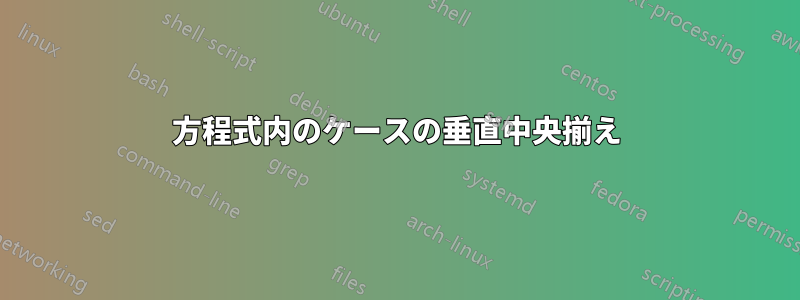
通常、単純な場合casesは以下の結果が得られます。
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{equation}
X=\begin{cases}
0, & \text{if $a=1$} \\
1, & \text{otherwise}
\end{cases}
\end{equation}
\end{document}
しかし、私の論文テンプレートでは、
\documentclass{article}
\usepackage{tabu}
\usepackage{longtable}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{setspace}
\setstretch{1.435}
\begin{document}
\setlength{\extrarowheight}{8pt}
\begin{longtabu}{ll}
\caption{This is a caption} \\
Longtable & Longtable \\
Longtable & Longtable \\
Longtable & Longtable \\
\end{longtabu}
\begin{equation}
X=\begin{cases}
0, & \text{if $a=1$} \\
1, & \text{otherwise}
\end{cases}
\end{equation}
\end{document}
デフォルトの行間隔を変更しました
\usepackage{setspace}
\setstretch{1.435}
行間隔を
\setlength{\extrarowheight}{8pt}
私の質問は、2つのケースをどのようにして中心に置くかということです。
答え1
の使用は、に基づく\setstretchにも悪影響を及ぼします。arraycases
ストレッチ係数の逆数にarray設定してパッチを適用することをお勧めします。\arraystretch
\documentclass{article}
\usepackage{tabu}
\usepackage{longtable}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{setspace}
\usepackage{etoolbox}
\setstretch{1.435}
\pretocmd{\array}{\renewcommand{\arraystretch}{0.69686}}{}{} % 1/1.435=0.69686
\begin{document}
\begingroup
\setlength{\extrarowheight}{8pt}
\begin{longtabu}{ll}
\caption{This is a caption} \\
Longtable & Longtable \\
Longtable & Longtable \\
Longtable & Longtable \\
\end{longtabu}
\endgroup
\begin{equation}
X=\begin{cases}
0, & \text{if $a=1$} \\
1, & \text{otherwise}
\end{cases}
\end{equation}
\end{document}
\extrarowheightこれは常にローカルに設定し、すべてのテーブルに適用されるべきではないと思います。





