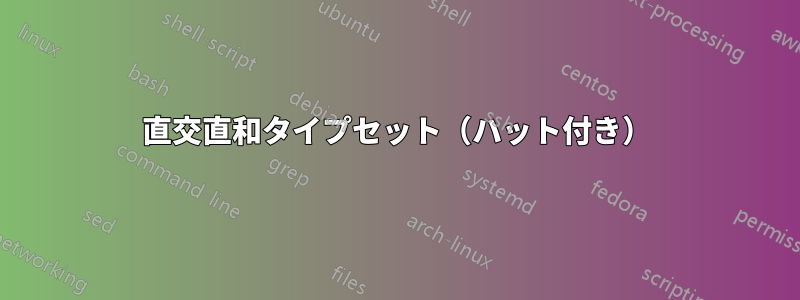
答え1
\documentclass{article}
\begin{document}
$U_1 \mathbin{\hat\oplus}\dots\mathbin{\hat\oplus}U_m$
\end{document}
の見た目が気に入らない場合は\oplus、独自のものを作成してください。
\documentclass{article}
\usepackage{stackengine,graphicx}
\stackMath
\newcommand\mysym{\mathbin{\hat{%
\stackinset{c}{}{c}{}{\scriptstyle+}{\scalebox{.8}{$\bigcirc$}}}}}
\begin{document}
$U_1 \mysym\dots\mysym U_m$
\end{document}
答え2
\hat{\oplus}生成するなどの構造アクセスペースの目的上、同じものとみなされる原子オード原子。したがって、目的の原子タイプを復元する必要があります。
マクロを定義することをお勧めします。
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\newcommand{\orthsum}{\mathbin{\hat{\oplus}}}
\begin{document}
\[
U_1\orthsum \dots \orthsum U_m
\]
\end{document}
シンボルは に関して正しく動作していることがわかります\dots。すべきこの場合はベースラインではなく中央に配置されます。
なぜマクロなのか?簡単に他のものに変更できるからです。直交直和の一般的な表記は⊞です。
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
%\newcommand{\orthsum}{\mathbin{\hat{\oplus}}}
\newcommand{\orthsum}{\DOTSB\boxplus}
\begin{document}
\[
U_1\orthsum \dots \orthsum U_m
\]
\end{document}
わかりました。これを正しく行うには、少し作業が必要です。
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
%\newcommand{\orthsum}{\mathbin{\hat{\oplus}}}
\makeatletter
\newcommand{\orthsum}{\DOTSB\mathbin{\mathpalette\boxplus@\relax}}
\newcommand{\boxplus@}[2]{\vcenter{\hbox{$\m@th#1\boxplus$}}}
\makeatother
\begin{document}
\begin{gather*}
U_1\oplus \dots \oplus U_m
\\
U_1\orthsum \dots \orthsum U_m
\end{gather*}
\end{document}
\oplus画像と同じスタイルを希望する場合は、 からシンボルをインポートできますmathabx。
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\DeclareFontFamily{U}{matha}{}
\DeclareFontSubstitution{U}{matha}{m}{n}
\DeclareFontShape{U}{matha}{m}{n}{
<-5.5> matha5
<5.5-6.5> matha6
<6.5-7.5> matha7
<7.5-8.5> matha8
<8.5-9.5> matha9
<9.5-11> matha10
<11-> matha12
}{}
\DeclareFontFamily{U}{mathb}{}
\DeclareFontSubstitution{U}{mathb}{m}{n}
\DeclareFontShape{U}{mathb}{m}{n}{
<-5.5> mathb5
<5.5-6.5> mathb6
<6.5-7.5> mathb7
<7.5-8.5> mathb8
<8.5-9.5> mathb9
<9.5-11> mathb10
<11-> mathb12
}{}
\DeclareSymbolFont{matha}{U}{matha}{m}{n}
\DeclareSymbolFont{mathb}{U}{mathb}{m}{n}
\DeclareMathSymbol{\oplus}{2}{matha}{"60}
\DeclareMathSymbol{\boxplus}{2}{mathb}{"60}
\newcommand{\orthsum}{\mathbin{\hat{\oplus}}}
%\newcommand{\orthsum}{\DOTSB\boxplus}
\begin{document}
\begin{gather*}
U_1\oplus \dots \oplus U_m
\\
U_1\orthsum \dots \orthsum U_m
\end{gather*}
\end{document}
コメントを切り替える\orthsumと










